| |
|
||||||||
|
悲しき熱帯(レヴィ・ストロース著)の真実 1 出発、探検、帰国、弱気 上 |
|||||||||
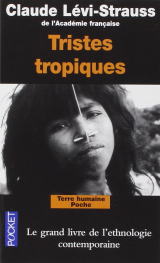 悲しき熱帯ポケット版 |
1955年に出版された悲しき熱帯(Tristes Tropiquesクロードレヴィストロース著)は作者の学生時期、旅、調査、亡命など1935年から20年の出来事、その身の変遷を思い出すままに書き連ねている。パリ洛陽の紙価を高め、名を世間に知らしめた作品です。表紙写真はPlon刊のポケット版。 本書について; 1 一人称で語りかけるレシ(récit)でまとまる。主人公「je私は」が流れを進める。書き出しもJeで始まる。 « Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais de temps pour m'y résoudre ! Quinze ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre » いかなる旅も開拓者たちも私は嫌いだ。今ここに己の探検譚を語るつもりになった。時が気分を変えたのだ、ブラジルから最後に出立してもう15年が過ぎた。この本を纏めようと時折、計画はしていた。(第一部Les fin des voyagesすべての旅の終わりの第一章Départ出発) 思い出すままの筋道は時空の流れも変幻自在、récitの語り口の投げる視点が足下にとどまる。読みやすい。 2 1954年、レヴィストロースはコレージュドフランス(Collège de France)教授職、人間博物館(Musée de l’homme)館長職の就任を学会の主流派(ノルマリアン:高等師範学校の卒業生で構成されるらしい)から拒絶された。彼はソルボンヌ学部卒。友誼の手を差し伸べたのがマロリー(Jean Malaurie、歴史地理学、イヌイット研究者、鯨街道allée des baleines,鯨骨を並べたカムチャッカ祭祀で著名、2023年7月現在100歳にて存命)。「人間の大地叢書Collection Terre Humaine」向けに「物語風学術書」の書き下ろしを依頼された。 |
関連するページリンク 悲しき熱帯の真実 1 同2 悲しき熱帯部族民の生死観1 同2  人間の大地叢書Collection Terre Humaine主宰 人間の大地叢書Collection Terre Humaine主宰Jean Malaurie 歴史地理学、イヌイット研究者、鯨街道allée des baleines,鯨骨を列に並べたカムチャッカ先住民の祭祀跡の発見で著名、2023年9月現在100歳にて存命 |
|||||||
| レヴィストロースはボロロ族をBonSauvageと評した。良き野蛮。 この表現は名詞の含意に逆の意味を持つ 形容詞を被せ、 受け取る側では意味の構築が難しくなる効果をねらう修辞。 Oxymore(oxymoronとも)形容矛盾とされる。文学表現では許されるが、学術書で用いてはならない言い回しであると批判された。 |
マロリー本人がこの叢書を創設し、配本第一回の「Thulé族最後の王」は自身の筆になる。第二回の出筆 依頼。人類学の資料価値を持ちかつ「一般読者が読める」が注文内容。当初3人称で執筆を予定したが、récitに換えた(本人の述懐YouTube、Apostropheから)。 1954年10月から、4ヶ月で書き上げた(奥付から)。これが今から70年ほど前、 3 497頁に及ぶ大作にはあるがフランス語初心者にも原書で読み下せる。面白さにのめり込む素直な読感こそ原文挑戦の報酬と言えるか。文体の魅力(多重否定、換喩法、洒脱さ)、思考の絡繰りが行間に潜む。 とある方が「リセ上級=高校生に理解できる程度」と判定した(と聞いた)。誠に正しい判定であろう。 完訳「悲しき熱帯」(川田訳)は河出書房から出版された。ネット通販で今も購入可能かと。 旅の始まり ; 大戦前のフランス国内事情。学部生の頃、主任教授(心理学Dumas)の風貌、一風変わった心理調査法。1934年ある秋の日曜日は朝9時、高等師範学校学長のBouglé(哲学、社会学)から突然の電話を受けた。 « Ma carrière s'est jouée un dimanche de l'automne. 1934. à 9 heures du matin, sur un coup de téléphone. C'était Célestin Bouglé, alors directeur de l'École normale supérieure. Avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie ? Certes1 alors posez votre candidature comme professeur de sociologie à l'Université de San Paulo. Les faubourgs sont remplis d’Indiens, vous leur consacrerez vos week-ends. 私の仕事歴は1934年秋のある日曜日の電話から始まった。ブーグレ、時の高等師範学校長だった。民族学を専攻したい気持ちは変わらないか。もちろん。それならサンパウロ大学の社会学教授の公募に申し込みなさい。あの街の街路いたるところにインディアンが生息している、週末に時間を掛けて調査できるぞ(47頁) 突然の電話に驚いたがその申し出にも驚いた « d’abord je n’étais pas un ancien normalien » 最初の疑問、私はノルマリアン(高等師範学校卒業者)の一人ではないのに。 サンパウロ大学教授に選任された経緯である。 学部卒のレヴィストロースはこの(公開のはずの)募集を知らなかった。なぜか部外のレヴィストロースに白羽の矢が飛んできた。応募しなさいとは言い回しで彼に決まっているも同然です。哲学系の若手として注視されていた、一目置かれていたと前向きに考える(このとき25歳)。 Bougléが自信をたっぷりに請け負った「サンパウロ街中にあふれる先住民たち」とは全くの虚構だと知った。サンパウロでは見かけなかったBororo族を訪ねに旅を組み、過酷な日程を経験することになる。本書は経時的に筋を辿らず、Bororo族などの探訪は別章になります。 1939年に帰国。まもなく第二次大戦、連絡将校として応召、そしてl’armistice=仏独休戦協定(1940年6月22日)、兵役の任を解かれ、住まうモンペリエに戻ってからフランス脱出までの経緯が語られる。 |
||||||||
|
レヴィストロースはユダヤ系で知識階層、占領下では拘束される怖れが多大に残る。 頭上を覆う暗い雲、個人では振り払えない。悩むレヴィストロースにアメリカの社会人類学者(Robert H Lowie)から「社会研究の新しい学校」への参加招聘状が届いた。ロックフェラー財団が進めている「ナチスドイツ占領による迫害から著名人を救済するプログラム」に選ばれたのである。(このあとVarian Fryによるユダヤ人救出作戦に選定される。ここは別投稿で) 舞台は帰国後に移る。レヴィストロースは悩む。帰国まもなく南米先住民調査発表が企画された。しかし状況は… « La société des amis du Muséum y organisait chaque semaine des conférences sur les sciences naturelles. L'appareil de projection envoyait sur un écran trop grand avec des lampes trop faibles. (パリ植物園の階段教室で開かれた「南米先住民の生態」なる一般向け講義、レヴィストロース講演と通知されたが)博物館友の会はそこで毎週自然科学の講義を開催する。幻燈器の光源は弱々しく、向かうスクリーンはとてつもなく大きく… 時間は迫るが教室には受講者の姿が一人も数えられない。 « Au moment où l'on désespérait, la salle se remplissait à demi d’enfants accompagnés de mère et de bonne, les uns avides dans changement gratuit, les autres laissent du bruit et de la poussière du dehors. Devant ce mélange de fantômes mités marmaille impatiente… » 誰も聞きに来ないー失望を味合う寸前に部屋は半分ほど埋まった。それは母親、女中に連れられた子供の一団だった。多くは無料で入り込める状況にワクワクし、もう一方は騒がしく、外の埃まで持ち込んでいた。(無言の女達)幽霊と辛抱できない子どもたちを前に…(11頁) 弱気のレヴィストロース(帰国の船旅) « J'avais quitté la France depuis bientôt 5 ans. J'avais délaissé ma carrière universitaire pendant ce temps. Mes condisciples plus sages en gravissaient les échelons, ceux qui, comme moi jadis, avait penché vers la politique, étaient aujourd'hui députés, bientôt ministres. Et moi, je courais les déserts en pourchassant des déchets d'humanité. Qui ou quoi m'avait donc poussé à faire exploser le cours normal de ma vie ? » フランスを離れてもう5年近くも過ぎた。この間、私は大学教師の経験を棒に振ったのだ。幾人かの同期生は私もそうしたかった政治に入って、私よりも賢いからすでに議員、いずれ大臣へと出世階段を登っている。そして私、村落の痕跡を探しに無人の地を走り回っただけ。一体何が誰が、私を押して、私の普通の人生を暴発させたのか(450頁)。 後にCollège de France Chair(フランス学院の教授) Académie翰林院の委員にも上り詰めるレヴィストロースにして、悔悟の弱気に苛まれたときも合ったのだ。 続いて <Ou bien ma décision exprimait-elle une incompatibilité profonde vis-à-vis de mon groupe social dont quoiqu’il arrive, j’étais voué à vivre de plus en plus isolé ? Par un singulier paradoxe, au lieu de m’ouvrir un nouvel univers, ma vie aventureuse me restituait plutôt l’ancien, tandis que celui auquel j’avais prétendu se dessolait entre mes doigts. (451頁) 訳;私があの決定をしたその時すでに、属している集団と深い亀裂が生じてしまったのだろうか。何が起ころうとも、どんどん孤立して行くのだろうか?わずかな食い違いかもしれない、それが私に新しい世界を広げる代わりに、冒険にかけたこの年月の成果が私を古い世界に戻してしまうのか。手に入れられるとした世界が、指の隙間から抜け出てしまったのか。 レヴィストロースがすっかり弱気になってしまった。 悲しき熱帯(レヴィ・ストロース著)の真実 1 出発、探検、帰国、弱気 上の了 (2023年10月1日) |
悲しき熱帯 巻頭のレヴィストロース 紹介。生没年、主な著作など Son oeuvre qui introduit le structuralisme emprunte à la linguistique... 作品を通して言語学から 借り入れた構造主義を 喧伝したが読める |
||||||||
| |
|||||||||
Jean Malaurie
歴史地理学、イヌイット研究者、鯨街道allée des baleines,鯨骨を列に並べたカムチャッカ先住民の祭祀跡の発見で著名、2022年1月現在99歳にて存命